4月 27 2016
言葉でも象徴でもなく、星たちの幾何学へ
Φさんがツイッターで素粒子について易しく丁寧に話をしていた。
―素粒子はフェルミオンもボソンも断じて「粒」ではない―
まずはこの認識をしっかりと頭に入れることが必要だ。つまり、世界は粒の集まりでできているのではない、ということ。こうした既成の認識を解体して、世界について根底から考え直す必要があるということ。
ヌーソロジーの考え方からすれば、素粒子とは「自他の即自的状況」に他ならない。創造世界はその関係性が無限の発展性を持つところに生まれている。思考とモノの相関関係を決して閉ざしてはいけない。その外部に思考が侵入することは不可能ではない。なぜなら、世界がこうしてあるのだから。
素粒子の粒子性とは空間の幅化がもたらしている一種の幻想であるということにそろそろわたしたちは気づくべきだ。空間の本性は奥行きに息づく純粋持続体であり、この視座の転換は知覚の現場を一気に無限小領域へとワープさせ、それまでの自他を精神としての「自他の即自的状況」の場へと遷移させる。
ここには小難しい哲学的議論はいらない。空間が延長であるという思い込みを外すだけでいいのだ。そのとき、わたしたちはすべての権力機構が延長概念によって供給されていたことを知ることになるだろう。自他の即自的状況にはいかなる権力も存在しない。
*****************************************
無限小へと降り立った知覚は対象を持たない。なぜなら、それは繰り広げられたものを表象ではなく、イマージュへと加工しているからだ。知覚はそこから襞を形成し、そのまま出来事の場へ捻られ、繰り広げの場を用意する母胎となる。
すべてが内内で、それこそ内密に事が進んでいるのだ。繰り広げが繰り広げの最中で知覚されたものが表出であり、そこではイマージュは再び表象となって姿を表す。そのとき、内に折り曲げられた襞の方は、表象=再現前化のシステムとして「潜在的に」働くのだ。
ライプニッツ=ドゥルーズが描くこの生成の襞なる生産機構は息を呑むほどに美しい。
この機構の明晰なる設計図が素粒子の群の構造と一致するならば、世界はそれ以上に美しい。この美的な完全性は果たして危険物として懐疑されるべき類のものであろうか。
確実に言えることは、やがて、否定と肯定という二つの思考の類型の間に激しい戦いが起こるであろうということ。そして、襞はその戦いの火花さえイマージュとして呑み込み、それを表現として繰り広げるであろうということ。たとえそれが破局的なものだとしても創造的なものだとしても、わたしたちにはその見分けがつかないだろう。
デジタルとナチュラルが混在する今の世界はまさに、その表現の場になろうとしているのではないか。
*********************************************
以前、死においては主体は1本の線(アンリ・ミショー)となると書いた。この線は非局所としての線のことだ。物理学的にはスピノルに相当している。線の理念と言い換えてもいいだろう。その意味で幾何学を思考することは死の組織化を思考するということであり、そこに幾何学と霊との直裁的な結びつきがある。
つまり、カタチを知るということは、霊的なものの復活なのだ。
主体を一本の線ごときに還元することに抵抗を持つ人も多いだろう。しかし、その線が有機的に他の死者たちと結合し、そこに真の物質の風景が立ち上がり、尚且つその風景が人間の現実世界と深い繋がり持つということになれば、私たちは現在の生を数倍、いや数百倍、数万倍にも輝かせることができるのではないか。
超越論的なものの幾何学というものが存在している。それは決して複雑なものではない、プラトンが指し示したように―。

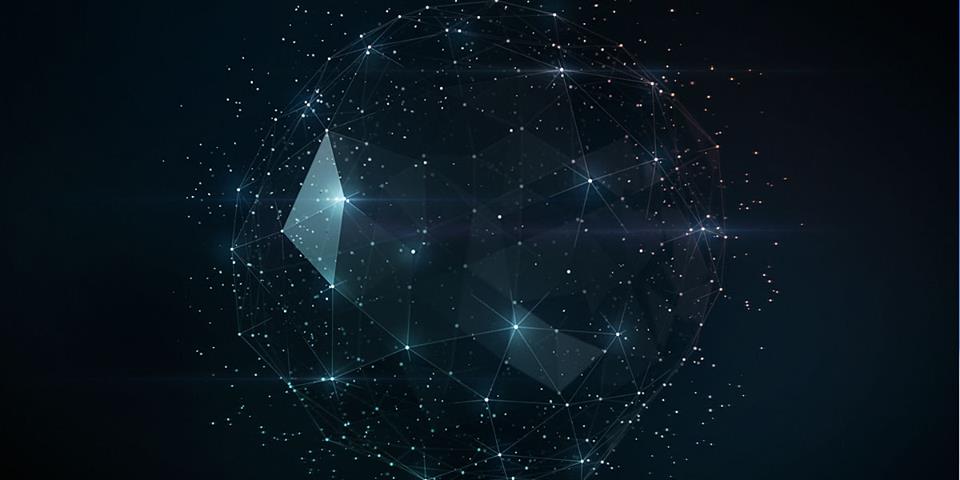






2016年5月1日 @ 13:29
この辺りと関係するのでしょうか?
「カムヒビキによれば、陰性電気を帯びた素量子一般がサヌキとよばれ、陽性電気を帯びた素量子一般がアワとよばれている。言いかへれば、サヌキアワの素粒子は、更に、その下に掘り下げられたいくつかの素量子で成り立ち、、、、、ここで素粒子というのは、素量子がいくつか集まったものの意であって、素粒子には大小があるわけである。、、、、、すべて、正反性の電気の『密度差』によって構成され、、、、」
「、、即ち原子核内の『微分空間』とも言ふべきものを質点とし、物質の『質量』は、その『アマナ』を構成するアメの密度即ち、トキトコロの粒子(潜態)の量によって定る、つまり、アマナの密度が少ければ質量は小さい、、、、」 (コビペできない〜(~_~;)。。。)
カタカムナ人、恐るべし!
熊本地震!
日本人のあまりのボケさ加減に 見るに見かねて ついに地が動き出した?
今こそ、E=mcc !
大丈夫!
空に〜太陽が〜あるかぎり〜♪♪(古 (^^;; )