9月 1 2008
時間と別れるための50の方法(32)
生命の樹と次元観察子の関係性(3)
さて、レジメ的になってしまいますが、ヌース理論の観察子概念と生命の樹の対応を取り急ぎまとめておきましょう。ここで紹介しておく内容は、あくまでもヌース理論から見たカバラ解釈なので、一般的なカバラ解釈と幾分齟齬を来しているところがあるかもしれませんが、古代より受け継がれて来たこの深淵な知識の謎を解明していくにあたって、ヌース理論からのアプローチはそれなりにかなり有用なものになるのではないかと思います。
まず、ヌース理論でおなじみのプレアデス(人間の次元)、シリウス(ヒトの次元)、オリオン(真実の人間の次元)という愛称を持つ三つの意識次元は、カバラでいうところのアッシャー界、イェッツェラー界、ベリアー界に対応すると考えていいでしょう(下図1参照)。アツィルト界はOCOT情報では「ヒトの上次元」と呼ばれ、真実の人間の意識がベリアーから意識進化を果たすときに入る次元です。この次元を真実の人間が完成させると、意識は「昇華」と呼ばれる作用によってその存在の必要性をなくし、何か全く別の領域に入るとOCOT情報は伝えています。
真実の人間の意識が覚醒を起こしベリアー界からアツィルト界に入るとき、同時に人間の意識はアッシャー界からイェッツェラー界に牽引されていくことになります。これが人間の意識進化に相当し、このとき月を中心に作動していたアッシャー界の中心位置としての「人間の無意識構造」はイェッツェラー界への牽引によって、今度は太陽を中心とした「ヒトの意識構造」へと変換させられていきます。これを「人間の意識の方向覚醒」と言い、意識がこの次元で働いている期間のことを覚醒期と言います。ヌースがいつも用いている言い方をすれば、潜在化として働いていた人間の無意識構造が顕在化を起こしてくるということです。顕在化=イェッツェラー界はその意味でアツィルト界によってコントロールを受けながら展開していくことになります。ヌース理論が現在関わっている部分はまさにこの部分です。
一方、生命の樹がベリアー界(コクマーとビナー)とアッシャー界を中心にして活動している期間のことをヌース理論では「調整期」と呼びます。この期間はルーリアカバラが言うように、ベリアー界の過剰な聖光によって中間領域であるイェッツェラー界はその機能を停止しています。それにももかかわらずなぜ最も下位に位置するアッシャー界が活動できるかというと、ベリアー界の力がダイレクトにアッシャー界に及ぶような円環構造が生命の樹には隠されているからです。
これはキリスト教的に言えば、父が聖霊を媒介とすることなく、直接、子と結合を持ってしまうような状態を意味します。ラカン的に言えば現実界が去勢され、象徴界と想像界が頑なに癒着している状態です。このような状態では、子の方から父へと繋がるメディアは存在せず(人間には創造の秘密が見えないということ)、父の子に対する一方的な支配関係が生まれてしまいます(人間が正体不明の神という存在に取り憑かれている状態そのものと言っていいでしょう)。まさに、ここにはユダヤ-キリスト教的な一神教の精神構造が反映されているわけです。人間が二項対立的な図式を原理とする言語活動に支配されているのも、この父-子癒着が原因となっていると考えられます。
神が上位で人間が下位。こうした目線の上下関係は、ケテルにおいて上向きの三角形(Ω11=冥王星)が登場してきたときに勢力を衰えさせ始めます。というのも、真実の人間の意識が自らの対化であるコクマー=Ω9とビナー=Ω10の関係を等化に持って行き始めるからてす。コクマー=Ω9とビナー=Ω10は生命の樹においては水平的な関係に位置していますが、その実質はベリアー界から見た、ベリアー界とアッシャー界間の双方向性、つまり生命の樹における〈下降-上昇〉関係を意味しています(図1のブルーとレッドの矢印を参照のこと)。
つまり、父(コクマー)が意識(アダム)をヒト(イェッツラー界)から人間(アッシャー界)に追放した存在だとすれば(ブルーの矢印)、母(ビナー)はその追放された人間をイェッツラーを通じて再び、自分たちの居場所へと引き戻そうとしている潜在力(これが意識です)になっているのです(レッドの矢印)。ですから、この文脈で言えば、「父(コクマー)と母(ビナー)が等化される」とは、父が母の意図を理解するようになるということであり、ここに至って、父は人間を人間に抑圧していた方向性を反転させ、自分たちの世界へと呼び戻すような精神運動を開始させます。このプロセスで人間は個体化を促進させ(Ω11=真実の人間における定質の働きです)、それと同時にその反映として人類=一つのものという概念を形成していきます(Ω12=真実の人間における性質の働きです)。人間における個的主体の確立と類的主体としての自覚。この両者がΩ11とΩ12としてのケテルの上向き三角形△と下向き▽が人間の意識に与えている役割だと考えるといいでしょう。
そして、Ω13がΩ11とΩ12を等化し、ケテルにおけるヘクサグラムの回転を促したとき、イエソドはティファレトへと反転し始めます。神秘学にいう「月と太陽の聖婚」です。母ビナーへの受胎告知とも言ってもよいかもしれません。それまで父のロゴスのみによって動いていた人間という次元は今度はヒトの次元へと向かい始め、今まで人間が死後の世界と呼んでいた場所(アッシャーにおける月(イエソド)が象徴している役割)が新たな生の世界(イェッツェラー界におけるアツィルト=Ω5)として開いてきます。OCOTが自らを冥王星の意識体と称し、自らの進化の一環として人間の意識進化を促して来た理由は自分自身がΩ13への等化の歩みを進め出したからかもしれません。
ビナーの受胎告知によって、宇宙的卵子(イエソド)に内在していた形態形成場の情報(潜在化していたヒトへの帰還の方向性)が、父のロゴス(理性)の侵入によりヌース(宇宙的知性)へと質的変容を起こし、月(イエソド)という巨大な宇宙卵の卵割(顕在化)を開始させていくわけです。こうして宇宙は覚醒期へと突入し、調整期とは全く違った局面に入ります。この目覚めによって人間の意識は中間を媒介するメディアであるイェッツェラー界を修復し、この宇宙的胎児を成長させるべくヒトの意識を発達させていきます。次の次元の宇宙的胎児の出産はヒトの意識がベリアー界へと進化するときに起こります。世界はそのとき刷新される………そういう筋書きになっているようです。
以上、現時点でのヌース理論からのカバラ解釈を取り急ぎまとめてみました。次回からは再び現地へと戻り、次元観察子ψ5~ψ6、ψ*5~ψ*6の顕在化について解説を始めることにします。ちなみに、このシリーズで今までお話ししてきた次元観察子ψ3~ψ4の領域をヌース理論が用いるPSO回路(ケイブコンパスの運動秩序を概観するためのマップ)におけるシリウスプレート内で表示すると、下図2のような位置に当たります。これからヌース理論が再生させていこうと考えているイェッェラー界(ヒトの世界)という領域がいかに広大なものであるかが直観的にせよある程度は分かっていただけるのではないかと思います。——つづく

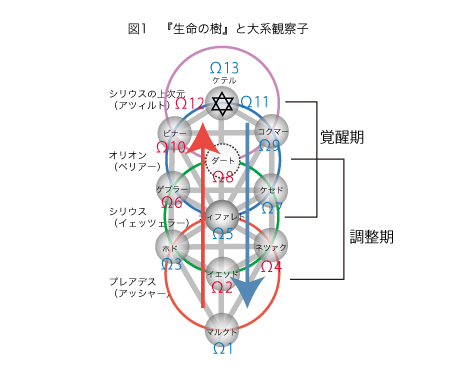
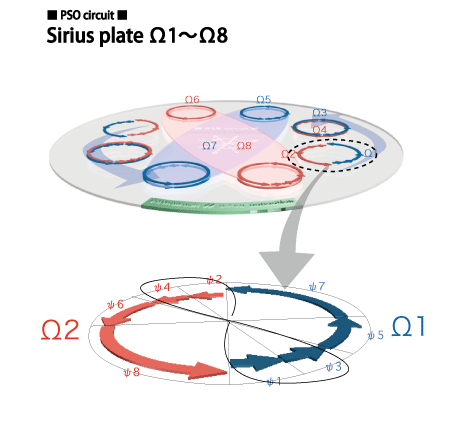






1月 19 2009
交信記録19940205
交信記録19940205
人間において食べるという行為は意識において何を意味しているのですか。
形作る次元を内面に生み出すということ。表相から内面に働きかけるということです。定質の対化によって元止揚を生み出していくためには必要な行為です。
元止揚とは何ですか。
反映としての覚醒作用を意味します。中和の交差の上次元に働かされるもの。変換作用が作り出されるときに働きに変えられるもの。人間の意識の方向性を反映から次元に変えるもの。
生態系における食物連鎖とは何ですか。
位置の交差の次元と反映が生まれるまでは必要な次元です。
変換人の次元に入るとものを食べなくてもよくなるのですか。
位置を形作る必要がないので食べるという行為はなくなります。人間の意識が上次元を関与するようになればそのような状態になるでしょう。
■解説
この交信内容に登場する内面、定質の対化、元止揚というのは、おそらく人間の意識次元におけるそれではなくヒトの次元におけるものだと考えられる。ヒトの意識構造は人間の意識構造と相似関係こそ持つものの、あくまでも比喩的な言い方だが約七倍の大きさを持っている。
人間の意識構造 ψ1〜ψ14
ヒトの意識構造 Ω1〜Ω14(まだ定かではない)
(ψ7=Ω1)
つまり、次元観察子ψ11が人間の意識の定質だとすれば、これはヒトの意識構造においては大系観察子のΩ5に相当し、ヒトの意識の定質はΩ11に当たる。その意味で人間がものを食べるという行為はヒトの意識の定質の対化であるΩ11〜Ω*11当たりに関係を持っているということになる。
食べることが肉体を保持するための必要不可欠な行為であることには違いないが、同時に、食べることは精神を保持するための行為でもある。一体、食べることの精神における本質とは何なのだろうか。わたしたちはなぜ生き物を食べるという、一見、残酷に見えるこの行為を必要としなければ生きられないのか——。
『シリウス革命』にも書いたが、OCOT情報によれば、自然界の生物とは人間自身が持った情念と思考の物質投影物ということになっている。植物が思考で動物が感情に対応しているというのだが、もしそれがほんとうならば、「わたし」が何かを思考したとき「わたし」は地球上のある種の植物へと変身しているということになる。「わたし」の中に怒りであれ、妬みであれ、喜びであれ、何かが感情としてうごめくとき、そのエネルギーは無時間の空間の中のどこかで純粋なアニマの形を取って、ある種の動物へと変態しているのだ。それは野をかける子ウサギのときもあれば、地を這い回るトカゲのときもあるだろう。
こうした考え方は何もOCOTの専売特許ではない。たとえば、ドゴン族の伝承では、ひとりの人間が死ぬとき、自然界のすべての動植物の一対もまた死ぬと言い伝えられていた。これもまた、人間の意識自身の中に全生物種のゾーエーが凝縮されているとする思想を反映している。
人間の内在野の中にある霊的自然。そこで連なっている霊的な連鎖体と、物質的生命としての生態系を重ねてイメージしたとき、無数の補食行為とはリゾーム状に張り巡らされた霊的なネットワークにおける交通空間の在り方のように見えないこともない。たとえば、悲しみの感情が慰めの感情により沈められたり、怒りの感情が冷静な思考によっていさめられたり、愛の感情が嫉妬の感情によって憎悪の感情に変わったりと、意識はつねに流動を繰り返しながら生成変化を行っている。この状態を動植物の間の食の流れと想像してみるのだ。一見、惨いことのように見える補食の行為もこうしたイマジネーションのもとでは生命システム自体が持った内部コミュニケーションのように見えてきはしないだろうか。
で、問題は人間だ。幸運にも今の人間は食物連鎖の頂きに立つ唯一の種として生きている。もし、人間という種が神の精神の投影物ならば、人間が経験する思考や感情はおそらく神が味わっている霊の果肉だということになるだろう。僕ら人間の肉が生態系から収穫された様々な食物を味わうように、その霊である神もまた人間の意識の中でさまざまな意識的果肉を人間の経験として味わっているということだ。その意味で言えば、この人間の身体にはありとあらゆる思考、そしておよそ想像される限りのすべての感情のもととなる情動のロゴスが充満していると言っていい。酸いも、甘いも、辛いも、苦いも、美味も、珍味も、そして毒も。。神の精神はその全肯定としての自身の履歴を生態系の多様性として反映させ、その完成を人間の身体として表現し、再び、今、始源の大地に立っている。。。
By kohsen • 04_シリウスファイル解説 • 2 • Tags: シリウス革命, ロゴス, 大系観察子, 表相