3、第三の軸――階段の男、もしくは上と下
さて、次に「階段に立つ男」についてフーコーがどう書いているか見てみよう。
彼がどこからきたのかはわからない。はっきりしない回廊づたいに、人々が集まり画家が仕事をつづけているこの部屋のまわりをまわってきたと想像することもできるだろう。あるいは彼自身、ついさっきまで、場面の前面、絵の中のあらゆる目が凝視している不可視の領域にいたのかもしれない。鏡の奥に認められる像とおなじように、彼も自明であるとともに隠されている、あの空間からひそかに使わされた使者かもしれぬ。といっても相違がないわけではない。彼はそこで生身の人間であり、表象されている区域の境界に外から姿をあらわしたところだ。彼はまぎれもない存在にほかならない。(M・フーコー『言葉と物』p.35)
階段の男からは画家の描く王の姿と実際の王の姿が見えていることだろう。そしてまた、彼の視野の中には画家の後ろ姿が確実に捉えられている。フーコーがいうように、もしこの男がこの部屋の中をついさっきまで徘徊していたとれば、壁に掛けられている小さな鏡の存在も知っているだろうし、その鏡に王が映り込んでいることも周知のことだろう。さらに言えば、この部屋にいるあらゆる人物と会話を交えながら、彼らの視座に近づいては王と画家の噂話を彼らの耳元で囁いていたかもしれない。となれば、このどこからきたのか素性がわからない男は、右の窓から差し込んでこの部屋を満たしている光の全体性を自らの眼差しの中に溶かし込んだ存在の象徴化とも言える。しかし、その眼差しはその光と同一のものというわけでもない。なぜなら、今、現在の彼の視線は右手に穿たれた窓の方からではなく画家の後上部にある階段奥の回廊から差し込んでくる光に沿うようにしてこの部屋に入射してきており、彼が立っている場所も部屋の中の諸人物たちよりも幾分高みの位置にあるからだ。そして、何より、この男を部屋の外部にまさに出て行かんとする存在として認知できているのは、この構図の中ではただ王(と王妃)のみである。
前回、左右方向からの視線は超越的なものだと語った。〈前-後〉と〈左-右〉が直交関係にある限り、この両者、つまり、〈わたし/あなた〉間を結ぶ視線とこの超越的な視線は互い重なり合うことは決してない。〈前-後〉は常に想像界のうちにとどまり、〈わたし/あなた〉という鏡像を巡って持ちつ持たれつの関係でだた主観的イメージの中で互いの間の乱反射を繰り返す。そのような意識状態に対して、左-右方向からの視線の入射は常に超越者として振る舞い、ときに審判の神として、ときに調停の神として両者の視線を同一化、均質化させ、第三項的眼差しを持ってこの〈わたし/あなた〉の間に介入する。このことは主観(内在)と客観(超越)が互いに対峙して双方その独立性を保ちながら作用していることを意味しよう。つまり、前-後の観察軸と左-右の観察軸が常時、直交関係を保っている限り、主観は客観を自らのうちに見いだすことはできないし、また、客観側も主観を自分の懐の中に入れることはできない。この作品に即して言えば、そもそも王の主観はそれが主観である限り、客観を形成し得ないし、客観は客観として神の座に座り続けたままで決して王のもとに舞い降りることはないからだ。
こうして意識が次の段階に進むためには「階段の男」の存在が極めて重要な役割を果たしてくるのが分かる——。
彼は部屋を満たす光と同じ視線を持った超越者の化身でもあったこと。
それゆえに彼は王を部屋の中の諸人物の中の一人として一般化させて見ることができているということ。
そして、これが最も重要なポイントでもあるのだが、彼は王によってのみ見られる存在となっているということ。
王から見える「階段の男」………これはまさにこの作品そのものの情景を視野空間の中に納めている王自身の主観の中に客観が入り込もうとしている様子と見なすことができる。主観が客観を自らのうちに内在化させようとしているまさにその瞬間の様子なのである。この「階段の男」の登場によって、超越者として振る舞っていた神の視線は王の眼差しの中に同一化を果たし、王は自らのうちに自分自身を客観視し、自分をみつめる超越者としてのもう一人の自分を自分の心のうちに迎え入れるのである。
この部屋の中で形成されている前後軸と左右軸が作る平面をヌーソロジーの考え方に沿ってとりあえずは5次元平面と比喩的に呼んでみよう。
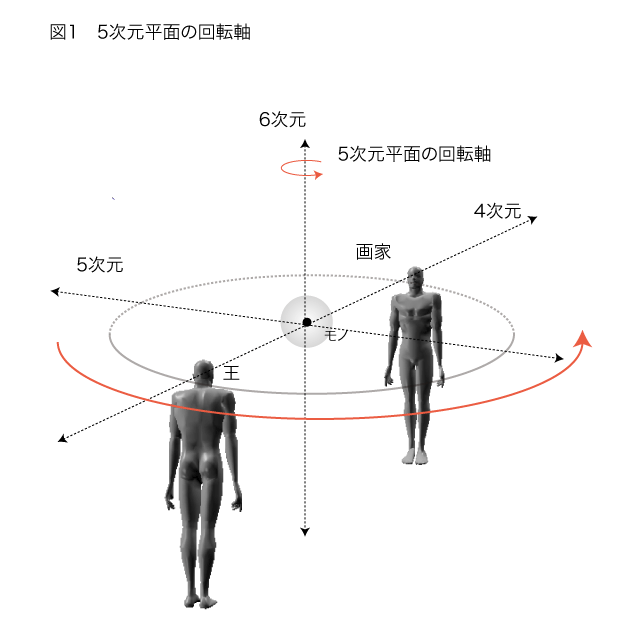
この高次の平面上で一体何が起こっているのだろうか――それはおそらく、王の身体における前後軸と左右軸を交換可能とするような回転が生じているのだ。この回転はそれまで全く対峙的に作用していた神的な視線と主観的視線の区別をなくす働きを持っていると考えられる。当然、その回転を行わせている軸が指し示す方向はこの5次元平面に直交する6次元の方向に向けられており、それはわれわれが普段、何気に上-下と呼んでいる方向ということになるのかもしれない。
全人類にとっての上-下という方向。それは意識平面としての大地を離脱し、地球の丸みを看破した観察の視線の方向とも言えるだろう。その意味で言えば、この絵に描かれた「階段の男」とはこの上-下方向への往来を可能とする観察力を持った6次元空間に座する超越者の姿だということができはしないだろうか。このニュータイプの超越者こそが人間の主観世界に同一化を果たした「我思う、ゆえに我あり」と語る我、すなわちコギトとしての近代的自我の本性なのである。バロック期から古典主義期にかけての時代にヨーロッパの画家たちの無意識は、〈左-右〉方向からの観察軸の成熟から〈上-下〉方向からの観察軸の確立へと向かったのだろう。ここから世界は一気に地動説的世界観へと突入し、地上を俯瞰するこの「階段の男」の視点の登場によって、神の理性のもとに生きていた人々は「理性的人間」という存在に変貌を遂げ、〈前-後〉軸を〈左-右〉軸と全く同等なものとして見ざるを得ない認識へと遷移していったのである。
この新たに設けられた視座が人間に何を招来させたかはもはや言うまでもないだろう。〈前-後〉方向と〈左-右〉方向の差異が全く認識できないのであれば、身体は他の存在物(物質)と同一な空間レベルに堕ちていかざるを得ない。身体空間が本来居住していると思われる4、5、6という空間次元は物質空間が息づく1、2、3次元と何も変わらないものとなり、そこから溢れ出た高次元の差異の力のみが、無意識という正体不明の言葉で呼ばれるようになったということだ。世界は今やこの「人間」が行使する3次元認識の暴力に悲鳴を上げている。無意識は再び目覚めなければならない。7次元からの使者の手によって。
——つづく







5月 5 2009
『ラス・メニーナス(侍女たち)』――人間型ゲシュタルトの起源、その6
3、第三の軸――階段の男、もしくは上と下
さて、次に「階段に立つ男」についてフーコーがどう書いているか見てみよう。
彼がどこからきたのかはわからない。はっきりしない回廊づたいに、人々が集まり画家が仕事をつづけているこの部屋のまわりをまわってきたと想像することもできるだろう。あるいは彼自身、ついさっきまで、場面の前面、絵の中のあらゆる目が凝視している不可視の領域にいたのかもしれない。鏡の奥に認められる像とおなじように、彼も自明であるとともに隠されている、あの空間からひそかに使わされた使者かもしれぬ。といっても相違がないわけではない。彼はそこで生身の人間であり、表象されている区域の境界に外から姿をあらわしたところだ。彼はまぎれもない存在にほかならない。(M・フーコー『言葉と物』p.35)
階段の男からは画家の描く王の姿と実際の王の姿が見えていることだろう。そしてまた、彼の視野の中には画家の後ろ姿が確実に捉えられている。フーコーがいうように、もしこの男がこの部屋の中をついさっきまで徘徊していたとれば、壁に掛けられている小さな鏡の存在も知っているだろうし、その鏡に王が映り込んでいることも周知のことだろう。さらに言えば、この部屋にいるあらゆる人物と会話を交えながら、彼らの視座に近づいては王と画家の噂話を彼らの耳元で囁いていたかもしれない。となれば、このどこからきたのか素性がわからない男は、右の窓から差し込んでこの部屋を満たしている光の全体性を自らの眼差しの中に溶かし込んだ存在の象徴化とも言える。しかし、その眼差しはその光と同一のものというわけでもない。なぜなら、今、現在の彼の視線は右手に穿たれた窓の方からではなく画家の後上部にある階段奥の回廊から差し込んでくる光に沿うようにしてこの部屋に入射してきており、彼が立っている場所も部屋の中の諸人物たちよりも幾分高みの位置にあるからだ。そして、何より、この男を部屋の外部にまさに出て行かんとする存在として認知できているのは、この構図の中ではただ王(と王妃)のみである。
前回、左右方向からの視線は超越的なものだと語った。〈前-後〉と〈左-右〉が直交関係にある限り、この両者、つまり、〈わたし/あなた〉間を結ぶ視線とこの超越的な視線は互い重なり合うことは決してない。〈前-後〉は常に想像界のうちにとどまり、〈わたし/あなた〉という鏡像を巡って持ちつ持たれつの関係でだた主観的イメージの中で互いの間の乱反射を繰り返す。そのような意識状態に対して、左-右方向からの視線の入射は常に超越者として振る舞い、ときに審判の神として、ときに調停の神として両者の視線を同一化、均質化させ、第三項的眼差しを持ってこの〈わたし/あなた〉の間に介入する。このことは主観(内在)と客観(超越)が互いに対峙して双方その独立性を保ちながら作用していることを意味しよう。つまり、前-後の観察軸と左-右の観察軸が常時、直交関係を保っている限り、主観は客観を自らのうちに見いだすことはできないし、また、客観側も主観を自分の懐の中に入れることはできない。この作品に即して言えば、そもそも王の主観はそれが主観である限り、客観を形成し得ないし、客観は客観として神の座に座り続けたままで決して王のもとに舞い降りることはないからだ。
こうして意識が次の段階に進むためには「階段の男」の存在が極めて重要な役割を果たしてくるのが分かる——。
彼は部屋を満たす光と同じ視線を持った超越者の化身でもあったこと。
それゆえに彼は王を部屋の中の諸人物の中の一人として一般化させて見ることができているということ。
そして、これが最も重要なポイントでもあるのだが、彼は王によってのみ見られる存在となっているということ。
王から見える「階段の男」………これはまさにこの作品そのものの情景を視野空間の中に納めている王自身の主観の中に客観が入り込もうとしている様子と見なすことができる。主観が客観を自らのうちに内在化させようとしているまさにその瞬間の様子なのである。この「階段の男」の登場によって、超越者として振る舞っていた神の視線は王の眼差しの中に同一化を果たし、王は自らのうちに自分自身を客観視し、自分をみつめる超越者としてのもう一人の自分を自分の心のうちに迎え入れるのである。
この部屋の中で形成されている前後軸と左右軸が作る平面をヌーソロジーの考え方に沿ってとりあえずは5次元平面と比喩的に呼んでみよう。
この高次の平面上で一体何が起こっているのだろうか――それはおそらく、王の身体における前後軸と左右軸を交換可能とするような回転が生じているのだ。この回転はそれまで全く対峙的に作用していた神的な視線と主観的視線の区別をなくす働きを持っていると考えられる。当然、その回転を行わせている軸が指し示す方向はこの5次元平面に直交する6次元の方向に向けられており、それはわれわれが普段、何気に上-下と呼んでいる方向ということになるのかもしれない。
全人類にとっての上-下という方向。それは意識平面としての大地を離脱し、地球の丸みを看破した観察の視線の方向とも言えるだろう。その意味で言えば、この絵に描かれた「階段の男」とはこの上-下方向への往来を可能とする観察力を持った6次元空間に座する超越者の姿だということができはしないだろうか。このニュータイプの超越者こそが人間の主観世界に同一化を果たした「我思う、ゆえに我あり」と語る我、すなわちコギトとしての近代的自我の本性なのである。バロック期から古典主義期にかけての時代にヨーロッパの画家たちの無意識は、〈左-右〉方向からの観察軸の成熟から〈上-下〉方向からの観察軸の確立へと向かったのだろう。ここから世界は一気に地動説的世界観へと突入し、地上を俯瞰するこの「階段の男」の視点の登場によって、神の理性のもとに生きていた人々は「理性的人間」という存在に変貌を遂げ、〈前-後〉軸を〈左-右〉軸と全く同等なものとして見ざるを得ない認識へと遷移していったのである。
この新たに設けられた視座が人間に何を招来させたかはもはや言うまでもないだろう。〈前-後〉方向と〈左-右〉方向の差異が全く認識できないのであれば、身体は他の存在物(物質)と同一な空間レベルに堕ちていかざるを得ない。身体空間が本来居住していると思われる4、5、6という空間次元は物質空間が息づく1、2、3次元と何も変わらないものとなり、そこから溢れ出た高次元の差異の力のみが、無意識という正体不明の言葉で呼ばれるようになったということだ。世界は今やこの「人間」が行使する3次元認識の暴力に悲鳴を上げている。無意識は再び目覚めなければならない。7次元からの使者の手によって。
——つづく
By kohsen • 01_ヌーソロジー, ラス・メニーナス • 0 • Tags: フーコー, ラス・メニーナス, 人間型ゲシュタルト