2月 27 2015
カタカムナ人の世界へ
相似象学会誌第四号を再読中。久々に読んだけど面白い。時間と空間に対する考え方がヌーソロジーと全く同じ。
「トキトコロは現代人の時間空間とは全く関係なく、物質の中に存在するマリ(粒子)であり、物質の質量といわれているものは、このトキトコロのマリの量によるもの云々」P.126。
空間や時間といった延長性がどのようにして微粒子の中へと入り込むかという仕組みがカタカムナ人には見えていたんだね。ただそれが「奥行きを通して」というところまでは、楢崎さんや宇野さんは思考していなかったようだ。
思考の場を奥行き=持続において、それ自身をカム(潜象化)と見なせば、アマ(延長性)とカム(収縮性)の接続のルートが開き、思考は自在にマリ(粒子)と化し、ヒビキ(霊引き)によって、アマナ(原子核)の構成の場所へと入って行ける仕組みになっている。それが複素空間における回転性だね。
そう考えると、現代物理学というのは潜象界のヒビキの地図作成術に携わってきたアマ側の活動のようなものだったとも言えるんじゃないかな。そして、そこに見出されたものがヤサカノマガタマ(七種の単玉)で、これを現代物理学は余剰次元としての7次元球面S^7として見ている。そんな感じだね。
でも、大事なことは、こうした知識を対象として所有することではなくて、やっぱり「それに成ること」なんだと思う。これがぶ厚いカベ。だから、自分を持続の中に溶かし込んで、持続そのものとなって思考する努力と忍耐が必要不可欠なんだね。
スピノザのように「永遠の相のもと」に、ベルクソンのように「純粋持続に身を投げ入れ」、メルロポンティのように「奥行き」において、ドゥルーズのように「非人称の主体」として思考する分身を内在性の中に育んでいくこと。これが霊性を思考する者にとっての絶対条件と言えるんじゃないかな。
でも、それって、すでに生きながらにして死んでいる者だったりして(笑)
そう、それでいいのだ(笑)。
生と死もまたマワリテメグルものなのだから。

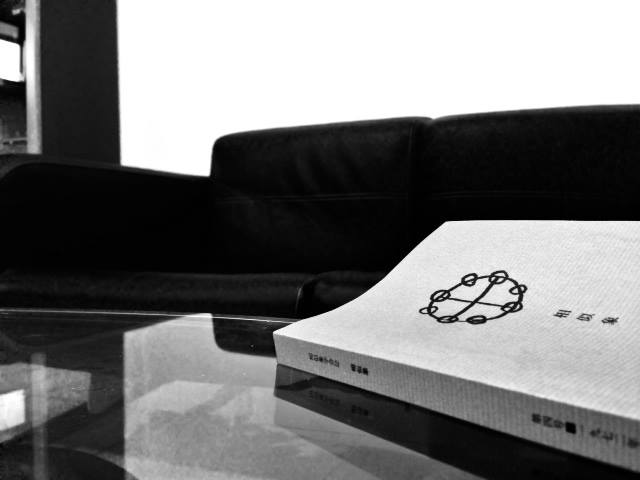






3月 13 2015
今日から、君がカタカムナだ!!(笑)
今日もカタカムナ関連で少しだけ。
アマとカムのムカヒというやつだけど、アマを「幅」に、カムを「奥行き」にダイレクトに当てはめていいと思うよ。ヌーソロジーでいう人間の内面と外面の対向性ってやつだね。これらはアカ(現象性)とアオ(潜象性)の関係でもあるね。つまり、NOSとNOOSってこと。NOSは赤色、NOOSは青色。よくできてる(^^)
現象の把握はアカとアオの混合から成っている。これをカタカムナは「アヤ」って呼んでいるようだ。「アヤしい=怪しい」のアヤ。「あやとり=綾取り」のアヤでもある。要は、混ざり合ってよく分からなくなっている状態のこと。これはベルクソンが言ってた「延長と持続の混雑」と同じこと。アカとアオの区別を認識に上げることが、いわゆるベルクソン=ドゥルーズのいう「差異」。
たとえば、目の前に3次元座標の空間を「イメージ」してみよう。この時点で、すでに幅と奥行きはヨコ回転したり、タテ回転したりして互換重合し、混じり合っている。ただ、人間の意識にはカム=奥行きの方は潜在化してしまって、アマ=幅が作り出す3次元空間だけが想像的な対象として浮上してくる。カムのほうは。このときミチ(持続)として働いているんだね。
「考える=カムカヘルとカムカエル」とはくだらないダジャレのようでもあるけど、とても本質をついている。人間に思考を強制させているもの、つまり、考えたくなくても考えざるを得なくさせているものとは、まさに、この潜象化している「カム」の力によるものだ。このカムこそが「思考サレルベキモノ(ドゥルーズ)」なんだね。
カタカムナに拠れば、アマは膨張性、カムは収縮性として働く。アマがカムに方向を持つことは「アマナ」と呼ばれ、「アマナ」はそのまま原子核の意となる。このへんは直球ストレートでほんとに気持ちがいい。幅として生まれでた現象性はカムのミチを通じて物質の根源へと回収されているってことなの。もちろん、この流動は人間の意識においては無意識化されているんだけどね。
OCOT情報は「カタカムナ文明とは前次元の覚醒期の知識です」と言っていた。楢崎さんはなぜそれが滅びたのは分からないと書いていたけど、それもまた「アマとカムの交替性によるもの」というのがOCOTの言い分。つまり、意識の在り方というもの自体もマワリテメグルものだということ。
まもなく、時代空間はアマウツシ(幅支配の世界)からカムウツシ(奥行き支配の世界)へと交替化を起こしていくよ。そうすれば、新しいカタカムナ文明が立ち起こってくることになる。ヌーソロジーの作業もまたその一つの息吹のように強く感じている。
カタカムナを学んでいる人は、是非、現代物理学やドゥルーズ哲学をゆっくりでいいので並行して学んでいくといいと思う。そして、それを知識として所有するのではなく、カム(奥行き=持続)を通してそれと一体化していく思念を育てて行くこと。そうすることによって明確なカタチ(構造性)と意志(新しい主体性)が生まれ、OCOT情報のいう「力(ちから)」が生まれてくる。ヌーソロジーが目指すのもそうしたカムナガラノミチそのものとしての身体性の獲得なんだね。だから——
今日から、君がカタカムナだ!!
なんか、カタカムナの宣伝マンになった感じ(笑)
By kohsen • 01_ヌーソロジー, カタカムナ関連, ドゥルーズ関連 • 0 • Tags: OCOT情報, カタカムナ, ベルクソン, 奥行き