2月 4 2009
コーラ、存在の子宮

●交信記録19940216
窒素の次元と陽子の次元の違いは何ですか。
付帯質の内面にあるものと、付帯質の外面にあるものとの違いです。
中性子の次元と酸素の次元の違いもその関係と同じなのですか。
はい。
宇宙空間と大気圏の関係もそれと同じと考えてよいですか。
はい、その通りです。方向が逆だということですね。
原子番号13番のアルミニウムから20番のカルシウムとは付帯質の変換を観察していく力ということになるのですか。
そうです。見つけ出すものを人間の内面に生み出していく力です。
見つけ出すものとは何ですか?
………………。
そこが真実の人間の次元と考えてよいのですか。
そうです。真実の人間の牽性(ケンセイ)が作り出す要請(ヨウセイ)によって、ヒトの外面性が生み出している力ということになります。
■解説1
窒素の次元と陽子の次元の違いは何ですか。
付帯質の内面にあるものと、付帯質の外面にあるものとの違いです。
中性子の次元と酸素の次元の違いもその関係と同じなのですか。
はい。
宇宙空間と大気圏の関係もそれと同じと考えてよいですか。
はい、その通りです。方向が逆だということですね。
ヌーソロジーにとって素粒子の世界とは哲学者たちが「場所」と呼んでいるものにかなり近い。曖昧で漠としたイメージではあるが、意識の中には確かに場所とも称したくなるような何らかの領域の区別がある。たとえば「わたし」について考えてみよう。「わたし」とは単なる生理的身体(肉体)のことを指すわけではない。だから、わたしという場所は、単に時空的な位置を指すものではないだろう。「あなた」についてはどうだ?あなたにしてもたぶん同じだ。あなたとはあなたの肉体のことをいうのではないし、あなたにはあなたがあなたであるためのあなただけの場所というものがある。その場所があなたを規定しているのだ。では、「わたしたち」や「あなたがた」についてはどうだろう?何か集団で議論をやっているとき、これも漠とした感覚ではあるが、賛成派と反対派の意識がまるで一つの一つの塊のようにして、それぞれ場所のようなものを持っているような気がするときがある。とすれば、外在世界という空間性もそれら意識における多くの場所の中の一つにすぎないのではないかという感覚が芽生えてくる。そうなると当然、今度は、時間の場所、歴史の場所、国家の場所なんてものがあってもおかしくはない。哲学者が場所と呼んでいるものとは、こうした存在論的な差異を形作っている場所のことと考えればいい。
こうしたどことも言えない「場所」という概念のルーツは、おそらくプラトンが『ティマイオス』で語った「コーラ(chora)」という概念に起源があるのだろう。プラトンにとって世界の本質はイデア界にある。その意味で、人間世界に現れた自然現象は洞窟の壁に映る影のようなものでそこには本質はない。つまり、自然界そのすべての営みが影=似像とされるわけだ。だから、思考にしろ、感情にしろ、自然界の似像を媒介にして営まれている表象や言語による人間の意識活動全般もまた本質に触れていないという意味で似像といってよいものだ。イデアを父なるものとすれば、自然界や人間の意識の生産物はすべて子なるものと呼んでいいのだろう。
さて、プラトンはこのイデアとその似像という二者関係の間に、第三項ともいうべき「コーラ(chora)」という概念を置いている。プラトンによれば、コーラは以下のような特徴を持つとされる。
1、生成物を入れる容器
2、無時間性
3、叡智的なものでも感性的なものでもない
4、火、地、風、水の四元素が存在するところ
5、五つの正多面体(プラトン立体)と関係を持つ
6、モノを占めている空間のことである(アリストテレス)
多くの研究者によれば、イデア=父、人間=子とするならば、このコーラは母に対応するものとされているのだが、ただ、その具体的な説明となると、どうも難解で、あのデリダさえも「われわれはまだ、受け取ること、この受容体が持つ〈受け取ること〉というのが何を言っているのかを、考えてはいない」と言っている。
意識に生み出されている様々な表象や言語、それらをバラバラに飛散させることなく、カテゴリー化させ、グループ化させて秩序立てると同時に、また解体し、接合させ、流動、循環、反復を繰り返し行なっていくような、生きた意識の原器の蠕動がある。その原器こそがコーラと呼んでいいものだろう。
さて、このコーラだが、ニュアンスから見ると、これはOCOT情報がいうところの「潜在化した元止揚」というものに極めて近い。僕が常々、人間の無意識構造と呼んでいるもののことだ。潜在化した元止揚は文字通り、人間の意識の生産物とは絶対的に隔絶された差異を持った何ものかであり、それは、生産されるものではなく、元から、そこにあり続けているものでもある。と言って、それはイデア(物質を創造した神の観念)とは少し異なる。なぜなら、潜在化した元止揚とは、あくまでも、人間の知性と感性の調整を行ないながら、最終的には個体を完成へと導いていく構造体であって、その間は、決してその正体を表さない、それこそ、神秘のヴェールに包まれた処女の裸体ごときものだからである。創造的知性としてのnoosが人間の意識に発現し、その元止揚を発見したときには、人間の意識はもう人間の意識と呼べる次元には存在しておらず、発見された元止揚そのものも、それは「顕在化した元止揚」として、「潜在化していた元止揚」とは別なものに変わってしまう。この発見された元止揚そのものがヌーソロジーがイデアと考えるものだ。つまり、この論理でいけば、発見されることもなく「潜在化した状態としての元止揚」は決して知性には現れることのない、まさにプラトンがコーラと呼んだものにふさわしい存在となる。
OCOT情報によれば、潜在化した元止揚とは人間という方向を進化の方向へと変換している場だと言う。また、それだからこそ人間には意識が持てているのだという。神話的に言えば、これは迷宮に入り込んだテセウスに巻き付けられたアリアドネの糸だ。人間自体はすべてが中和された場に、観察精神の付帯質=肉体として生み出されており、それが投げ込まれているところは時空という光なき漆黒の領域である。OCOTによれば、この闇の領域に人間の意識を突っ込ませているの力が重力であり、この重力は質量と結託して物質という幻想を時空の中に凝結させている。その意味で言えば、重力とは父の力そのものであり、父によって子は水〈3次元性〉の中に沈められ、洗礼を受けているということになる。この方向を水上へと変換しているのが、潜在化した元止揚と呼ぶもので、それは物理的に言えば、重力に抗う素粒子群が持つ力に相当している。10年前の『人神』から一貫して言い続けているように、重力と素粒子の力は方向性が全く逆なのだ。
ヌーソロジーでは重力が働いている領域は人間の内面の意識領域と呼び、素粒子が働いている領域は人間の外面の意識領域と呼ぶ。これら両者を合わせたものが「付帯質の外面」の次元となる領域である。付帯質の外面においては人間の意識の変換性は働いているものの、それはあくまでも潜在化しているがゆえに、明確に知性の対象となることはない。いわゆるこれがコーラ=潜在化した元止揚だ。しかし、時が巡ってくると、知性はその方向性をその潜在性へと向け始める。永遠の処女はその股間を開き、ロゴス(種子)を迎え入れ、母なるものへと変身を果たすのだ。この母としての領域がOCOTが付帯質の内面と呼んでいるもののことだ。いわゆる元止揚が顕在化してくる領域のことだ。コーラとして存在させられていた素粒子構造は、この劇的な変身によって、原子番号1番から14番までの元素へとその姿を変えていく。ここが顕在化した元止揚が働きを持つ領域、すなわち、シリウス(ヒト)という場になる。
1、付帯質(フタイシツ)の外面、内面という表現の由来
付帯質とは外在として僕らがモノと呼んでいるもののことです。僕らは普段、自分自身をモノの外部に措定して、そこからモノを見ていると考ています。つまり、現在の僕らの常識では、人間はモノを外からしか観察できない宿命を持っているわけです。このときにいうモノの外というのが付帯質の外面の意味だと思って下さい。付帯質の外面においては内在世界というものは、さっきも言ったように、非常に曖昧な場所としてしか感受できません。こういう場所の曖昧さをOCOTは「人間の意識が持った不確実な方向性」と言っています。つまり、人間の意識は内在の場所を空間のかたちとして示せないわけです。こうした状態が、先にお話しした潜在的な元止揚が活動している状態です。
付帯質の外面がモノの外部だったわけですから、付帯質の内面とは、当然、モノの内部ということになります。つまり、人間が自分はモノの外部にいるのではなくて、モノの内部に存在しているのだ——と考えるようになったときの意識の場所の総称です。主体がこのモノの内部に位置を持つためには、人間の外面の意識(潜在化した元止揚)を覚醒させる必要があります。その第一歩がいつも言っているように、知覚正面自体を人間の主体そのものだと考えることに当たります(位置の交換)。
2、付帯質(フタイシツ)の内面へと移動する方法
知覚正面は『時間と別れるための50の方法』で何度も説明してきたように3次元空間の中に含まれるものではありません。それは正の4次元方向(4次元空間)にあるものです。知覚正面にある奥行きを遠い世界として考えると、そこにはまず時間が入り込んできます。つまり、遠くのものは過去と同意となり、奥行きは時間という負の4次元を重ね合わせてくるわけです。しかし、知覚正面そのものに映し出されている像そのものはベッタンコであり、そこには奥行きは存在していません。いかに遠くの世界であれ、知覚正面ではココにあるわけですから、このココは過去から現在に至るまでの時間をすべて含んだココになっていると考えられます。ヌーソロジーの考え方は、そうしたココこそが主体の位置ではないのか、と言っているわけです。その意味でこのココは時間を持ちません。4次元の長さが限りなくゼロに近いところまで縮められているということです。ですから、何かモノを見た場合、知覚正面上での視線は3次元的な感覚で言えば、すでにモノの中に入り込んだただ方向だけを持った極小の線のようなものになってしまいます(スピノール)。これが付帯質の外面から付帯質の内面へと移動する方法だと考えて下さい。4次元の人間は自在にモノの中と外を出入りできるのです。
写真はウォーターハウス「アリアドネ」(http://blog.goo.ne.jp/chimaltovより借用)







6月 18 2009
地球から広がる空間について、その8
地球から広がる空間についてダラダラと駄弁を弄してきましたが、ここで地球、月、太陽が精神構造においてどのような役割を持っているのかについて簡単にまとめておきます。今まで示してきた地球や月の自転、公転の話ともいずれドッキングしてきますので、それが楽しみに思える方はどうぞ楽しみにして下さい。
まとめの前に、まずは僕の会社の取引先の会社の通信誌に掲載されたインタビュー記事を紹介しておきます。この記事は毎回、映画をネタにヌース話をくっちゃべる「NOOS DE CINEMA」というコーナーで、『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』を題材にしたときのものです。
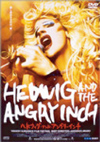
ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ
「人間は一体どこに向かって、一体何をしようとしているのか?」
今回のヌースDEシネマは「ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ」を題材にヌーソロジーの独自な視点で語っていただきます。
* * * * *
藤本 今回の映画は、オフ・ブロードウェイで大ロングランを記録したロック・ミュージカルを映画化した『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』です。デヴィッド・ボーイやマドンナなどのロックスターもオフ・ブロードウェイでミュージカルを観劇しています。デヴィッド・ボーイはその後ロス公演に出資したりマドンナは劇中で歌われている曲の2曲を自分のレーベルからリリースしたいと申し出たそうですね。
半田 とにかく楽曲が素晴らしかったね。特にテーマ曲ともなっている『愛の起源(The origin of love)』はミュージカル史に残る名曲だね。作曲を担当したスティーブン・トラスクもバンドのギタリスト役で出演してる。サウンド・トラックを買っても損はしないと思うよ。
藤本 そうそう僕もCD買いました。ツタヤで借りようかなと思ってたら、半田さんに強く勧められて、博多のキャナルシティに一緒に行って買いましたね。(笑) どの楽曲もとても素晴らしいと思います。その中で『愛の起源』は一番気に入っています。この曲はプラトンの『饗宴』にモチーフを得た寓話を物語としてバラードにしたとCDの説明書に書いていました。
半田 そうなんだよね。『響宴』での議論のテーマが「愛」だったんだ。その中でソクラテスがまず愛を永遠のイデアとして語るんだけども、アリストファネスが語った愛の起源の寓話の方が有名になっちゃったんだよね。世界が生まれたばかりのころの人間は二人一組で背中合わせの生き物で、両手両足がそれぞれ4本ずつあった。しかし、人間が地上を支配するのを嫌った神さまは、この最初の人間を二つに引き裂き、それぞれ今の人間の形にした。以来、人間は失われた半身を求めて愛を渇望するようになった。という話だね。テーマ曲の『愛の起源』はそのストーリーをとても分かり易くアニメ仕立てにしていて、映画のセンスをぐっと引き立てていたよね。
藤本 その話なんですけど、今の人間が生まれる前=愛が生まれる前=人間が二人一組だった頃は「三つの性」があった。男と男が背中合わせだと『太陽の子』。女と女が背中合わせだと『地球の子』。そして『月の子』はフォーク・スプーン、太陽と地球、娘と息子の中間。今は男と女だけど、この「三つの性」について解説していただけますか?
半田 この三つの性というのはね、世界というものが生まれるための三位一体を象徴させて言っていると考えていいんじゃないかな。まず男・男の『太陽の子』というのは精神、女・女の『地球の子』というのは物質、そして男・女の『月の子』が意識。物質と精神をつなぐものが意識なんだけど、今の人間は人間自体の精神が自己と他者という双子関係で作られているということに気づいていないので、世界の成り立ちを単に男性原理と女性原理の二元論で見ちゃってるんだよね。それだと両性具有的な原理が見えない。結果、精神と物質が対立してしまう。そして間をつないでいる両性具有の部分が無意識の中に沈んでしまうんだね。月はその沈んでしまった無意識を象徴するものなんだよね。
藤本 男・女の『月の子』は、物質と精神をつなぐ意識であり、両性具有的な存在と考えていいのですか?映画の中で主人公のヘドウィグは、西ベルリンで男として生まれ育ちますが、アメリカの兵隊に求婚され、アメリカに渡るために性転換手術をします。その手術が失敗して傷跡が1インチ隆起してしまう。題名になっているアングリー(怒りの)インチ(1インチ)。ヘドウィグは、『月の子』ですね。
半田 主人公のヘドウィックがゲイだという意味ではそうだね。しかし、別の解釈もできる。そもそもこの作品が面白いのは至るところに月に象徴される人間の無意識世界を目覚めさせろというメッセージが様々な比喩となって盛り込まれているところなんだよね。たとえば、ヘドウィッグが歌う挿入曲の『ヘドウィグ&アングリーインチ』では「オレのオチンチンはもともとは6インチあった。それが1インチだけ残されてしまった、こんな半端な状況で一体どうしてくれるんだ!!」ってその何ともやりようのない怒りを歌ってる。これは全体の5/6がどこかに消えてしまった中途半端さに対する怒りなんだ。5/6というのは10/12でもあるんだけど、「12のうちの10がどこかに消えてしまった」という話は古代の宇宙論ではよくある話で、たとえばユダヤの「失われた10支族」の伝承なんかもそうだね。12で完全なのになぜか2しか残っていない。残りの10を探さなくてはならない、ってね。12のうちの2というのは不吉さを表していて、東洋占術なんかでも天中殺で使われてる。ヌーソロジーの宇宙観もそうだよ。
藤本 奥深い話ですね!では顕在意識が2で残り10が潜在意識。そしてこの映画のテーマは、「人間の無意識世界を目覚めさせろ」ということですか?どうしたら人間の無意識世界が目覚めるんでしょうか?
半田 ズバリ、最初に紹介したこの映画の主題曲でもある『愛の起源』の中にそのヒントは隠されているんじゃないかな。『愛の起源』の中で、もともと人間は背中合わせでくっつき合っていて、手足が各4本ずつあったと言ってる。このことが何を意味しているか、そのナゾを解くということだよ。実際、こうしたことを言ってるのは何もプラトンの『響宴』だけでなく、アフリカのドゴン族の神話にもノンモという生物がいて、これまた男・女の背中合わせのかたちをしてるんだ。日本にも両面スクナという伝説が残っているしね。
藤本 そうなんですか。アフリカや日本やでもそのような神話が残っているのですね。手足が4本ずつある意味って何ですか?それが「人間の無意識世界を目覚めさせる」ことと関係あるんですよね。
半田 これはヌーソロジーの根幹とも関係があることなんだけど、人間という生き物は本来、自己と他者で成り立っているということなんだ。つまり、ほんとうは二人で一人であって、個体が独立して存在しているように考えるのは誤りだということ。おそらく、大昔はそうした「二人で一人」という人間像が当たり前に思える意識状態で人間が存在していたのかもしれない。もっとも、それを人間と呼べるかどうかは分からないけど(笑)。
藤本 手足が4本とは、自己の中に他者が存在している。自他共にひとつであると言うことですね。それを神が引き裂いた。他者を取り戻そうとすることが愛ということですか?
半田 他者を取り戻すとも言えるし、ほんとうの自分を取り戻すとも言えるよね。なぜなら、自己とは他者によって与えられているものだから。『愛の起源』が語る背中合わせの男・女とはその意味で言えば、愛を成就した人間のかたちそのものと言っていいのかもしれない。愛が成就しているのだから、そこには愛なんてものはない。今の人間が愛と呼んでいるものはそうした失われた半身を取り戻そうとするあがきのようなものかもしれない。
藤本 「人間の無意識世界を目覚めさせる」・「ほんとうの自己を取り戻す」ことは、「愛を成就した人間のかたち」・「手足が各4本ずつあった」・「6インチあった」・「12」に戻ることですよね。この映画は、ヘドウィックが今の人間として、その道を彷徨っている姿を描いているのだと思います。
半田 そうだよね。その意味で言えば、愛が成就できない今の僕らはすべてがヘドウィグであり、そこに怒りや苦しみをぶつけるアングリーインチとも言えるね。
藤本 ヘドウィグは、現在の人間の象徴的存在ですよね。この映画の最後のシーンで、ヘドウィックは、化粧が剥がれ落ち、カツラを取り裸になって、雨が降る夜の街角をフラフラと歩いていきますよね。最後のシーンとしては、寂しい終わり方です。これも何か意味があるんですよね。ヘドウィグは、どうなるのでしょうか?凄く気になります。
半田 そうだね。一見するとこの映画は、結局「人間は魂の片割れを追い求めて永遠にさまよい続けるしかない」というメッセージを発しているように思えるけど、僕は違う見方をしてるんだ。ラストの少し前のところで、ヘドウィグが女装を脱ぎ捨てて男の姿に戻って額に十字架を描いて歌うシーンがあるよね。そのとき衣装は純白に変わっている。このシーンは実は無意識の覚醒を描いたものじゃないかと思うんだ。だから同時に、ヘドウィグと対照的な関係にあったイツハク(彼女はいつも男装をしていた)も、本来の女自身の姿に戻り、隠されていた美しさを開花させる。ここはこの作品でも一番大事なところで、本来の男と女に戻った人間の姿が現れているとこなんだ。さっき言ったよね。今の人間は皆がアングリーインチなんだって。つまり、「無意識を目覚めさせる能力」が去勢されて、悩み苦しんでいる。だから、本来の男と女に戻るということは、無意識の目覚めを寓意させているんだよね。そして、この映画が素晴らしいところはそこで物語を終わらせなかったところ。無意識がたとえ目覚めて愛が成就したとしても、また、別れがやってくる。最後にヘドウィグが雨の街を裸で放浪するシーンはその意味で「新しい始まり」と解釈した方がいいだろうね。そうやって、世界は流転し続けているんだと。決して愛が究極ではなく、成就した愛は、また別れの物語を作り上げ、人間という存在のストーリーは永遠に続いて行く。愛の成就というゴールよりも変化していくプロセスこそが最も大事なものなんだよ。—— 「いきいき生活通信」 2009年5月 1日号より転載
ということで、次回、地球、月、太陽の話を、架空のインタビュー形式にして続けてみることにしましょう。次回はコテコテにヌースロジカルに話します。
By kohsen • 01_ヌーソロジー, 09_映画・テレビ • 0 • Tags: プラトン, ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ, ユダヤ